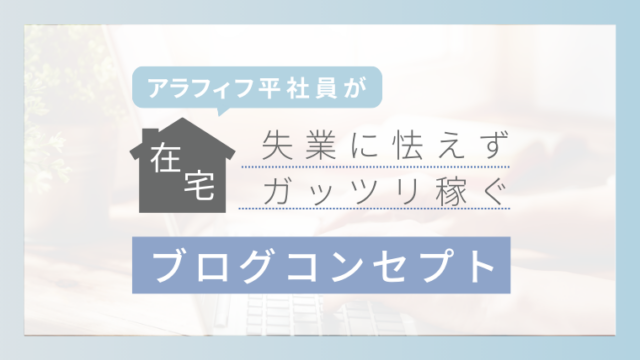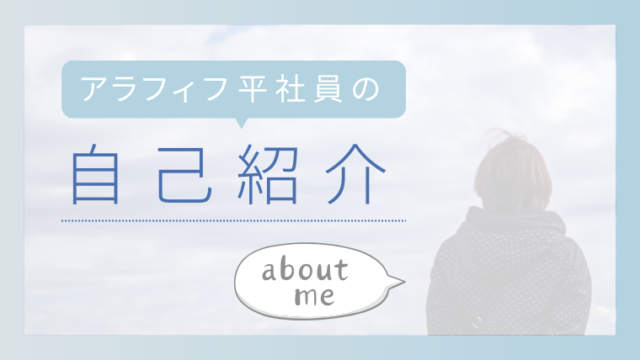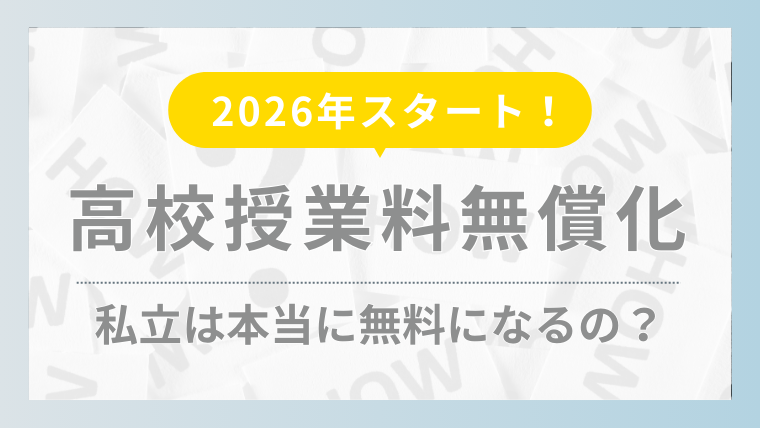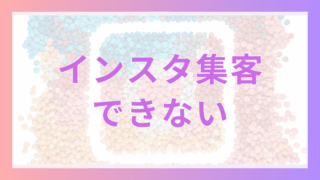こんにちは、もちこです。
2025年から全国で公立高校授業料無償化されましたね。
さらに来年度(2026年4月)からは、私立高校でも就学支援金の上限額が引き上げられ、最大45万7,000円まで支給される予定です。
子供の進学の選択肢が広がる!
そう期待しているご家庭も多いのではないでしょうか。
でも実際のところ、
うちは対象になる?所得制限て何?
そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
私もまさにその1人でした。
今年公立高校に入学した子供がおりますが、入学時に渡された大量の書類を前に、
と正直かなり混乱しました。
なんとか、なんとか読み解き書類を提出でき、無事授業料を無償にできホッとしました。
2026年、来年はいよいよ私立も無償化の対象が拡大。
子供たちの選択肢が広がることはうれしいけど、やっぱり「私立高校=お金がかかる」イメージはなかなか消えませんよね。
例えばこんなことありませんか?
「私立に行きたいんだけど」
→学校見学に行った子供から言われて焦る。
「公立行くけど成績がギリギリ。もしも落ちたら…」
併願の準備、でも私立ってどのくらいお金がかかるの?
私も「私立って高い」というイメージはあっても、実際にどのくらい費用がかかるのかは全然ピンと来ていませんでした。
それに、公立だって塾代など、高校受験の時だって結構お金がかかったのに、高校生になったら一体いくらかかるの?
未知すぎて不安でいっぱい。
「公立でいいだろ」学校のことはノータッチのパパは、子供の気持ちまで考えてくれない。
このモヤモヤを共感してくれる人も多いはず。
そんな中で知った「高校授業料の支援制度」。
お恥ずかしい話ですが、私、手続きなんて必要なく、勝手に無償化してくれると思い込んでいました。
でも実際には、きちんと申請が必要。
いざ書類を目の前にすると、
「これは何の書類?どういう意味?」と何度も読み返して「これで大丈夫?」と不安でいっぱいでした。
ここでわかったことは
📍所得制限は一つの目安に過ぎない
📍公立と私立では支援の内容がまったく違う。
ということでした。
そして何より、公立はお金がかからないなんて大間違い!
公立でもまとまった費用しっかりかかるんですよね。
この記事では、私の体験を交えながら
📍高校授業料無償化の最新情報
📍私立・公立の違い
📍所得制限と課税所得の仕組み
📍いつお金が必要になる
このことについて、わかりやすく解説していきます。
これから高校選びをするご家族が、「うちはどうすればいい?」と迷わないように、少しでもお役に立てたらうれしいです。
高校授業料無償化の最新情報まとめ

まずは今年2025年に始まった公立高校授業料無償化と来年度からの変更点について最新情報をお伝えしていきます。
2025年公立無償化の全体像と変化点
高等学校等就学支援金は〈世帯年収約910万円未満〉が対象。
公立の場合は年11万8800円(授業料相当)が学校に支給され、実質無償に。
年収910万円以上世帯は支援対象外なので、公立授業料(年11万8800円)を自己負担。
低所得世帯向けの「奨学給付金」や、都道府県独自の上乗せ補助は別制度として運用。
所得制限を撤廃。年収に関係なく〈すべての世帯〉へ年11万8800円が支給されるため、公立高校の授業料は完全無償に。
910万円以上世帯も授業料はゼロ。ただし、申請は必須(申請しなと支援金が入らない点は従来どおり)。
無償化後も「奨学給付金」などは継続。教材費・修学旅行費など授業料以外をサポート。
2025年からの改善ポイントは、世帯年収がいくらでも公立授業料は国が全額負担してくれるようになりました。
手続きの方法は、学校を通して就学支援金を申請する書類手続きがあり、申請し忘れると自己負担になってしまうので注意が必要です。
授業料以外の、入学金、制服代、教材費、部活動費、通学費などは従来通りで、負担がゼロになるわけではありません。
我が家では入学時に授業料以外の費用を30万円ほど支払いました。
ですので、まとまった金額の出費に備えておく必要があります。
2025年度では公立の授業料無償でしたが、2026年で予定されている変更点をみていきましょう。
2026年私立無償化の予定と支援内容(地域差も含む)
1. 国の新制度(2026年4月開始予定)
2026年度から予定されている「私立高校受領料の実質無償化(就学支援金拡充)」の全体像を、現時点で分かっている地域ごとの支援についてはこちらです。
| 変更点 | 2025年まで | 2026年度から(予定) |
|---|---|---|
| 限額 | 年39万6000円(私立平均より低い) | 年45万7000円に引き上げ (私立全国平均授業料相当) |
| 所得制限 | 世帯年収約590万円未満のみ 加算対象 |
所得制限を撤廃 すべての世帯が対象 |
| 法的手続き | 現行の就学支援金制度 | 2026年度予算と通常国会で関連法改正予定(自民・公明・維新の3党で合意) |
来年度では、45万7000円を超える差額が自己負担となります(入学金や・制服代・教材費は国の無償化対象外)。
申請手続きは現在と同じように学校経由となる見込みです。
2. 都道府県ごとの上乗せ支援(2024〜2025年度時点)
国の支援とは別に、2025年度時点で、特に支援の大きな自治体についてお伝えしていきます。
| 地域 | 支援上限・特徴 | 所得制限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 年 48万4,000円まで支援 (都平均授業料相当) |
なし (2024年度から撤廃) |
申請はオンライン中心 東京都交通局 |
| 大阪府 | 年 63万円まで支援 (全国最高水準) |
なし (子どもの人数に関係なく) |
在住要件:毎月1日時点で 生徒・保護者全員が府内在住 大阪府ホームページ |
| 神奈川県 | 授業料 46万8,000円、 入学金 21万1,000円まで補助 |
年収目安 約700万円未満 (多子世帯は910万円未満) |
国支援と合算で実質無償化可 神奈川県公式サイト |
| 愛知県 | 国支援に上乗せし、年額最大44万5,200円(1年生)補助 | 課税標準額に応じ段階制 (目安:年収600万円弱まで手厚い) |
家計急変用の追加補助もあり 愛知県公式サイト |
東京都・大阪府では差額もほぼカバーできる支援の体制が整っているようですね。
その他の県では、国の45万7000円+県独自補助でほぼ無償になるのは低~中所得世帯が中心になるようです。
入学金補助の有無も県によって大きく違うので、ご自身の住む自治体ごと確認が必要になります。
・県教育委員会・「私立高校授業料減免」ページ
・学校の募集要項(県の上乗せ額と併記されていることが多い)
・市役所の子育て・教育費支援窓口
このような情報を合わせてチェックしてみると各自治体ごとの国の支援にプラス支援を確認してみることをお勧めします。
3. 進学先を選ぶ前のチェックリスト
私立高校は、入学時にかかる費用、入学してからかかる費用が学校ごと、コースごとにシステムがそれぞれ違います。
以下のチェック項目を確認してみると実際どのくらい費用がかかるのかイメージしやすくなると思います。
1.授業料(年間)と校納金を必ず確認
学校パンフ・説明会で「授業料総額」と「その他費用」を一覧でもらう。
2.県独自の補助額を合算し、45.7万円を超える部分を計算
東京都・大阪府ならほぼ全額カバー、それ以外は差額を自己負担。
3.制服・施設費・タブレット・遠征費など“非授業料コスト”を足す
入学初年度は私立で50万〜80万円、公立でも15万〜30万円程度かかる例が多い。
4.世帯の課税所得をチェック
控除(iDeCo・保険料控除など)で支援対象に入るケースも。
5. 大学進学費用も並行して試算
私立大進学なら4年間で最低400万~、国公立でも250万~が目安。
まずはお子様がどこの学校に行きたいのか、また希望する学校の様子や資料を調べることが大事です。
それを知ったうえで、実際払う総額は
授業料差額+入学金+制服・塾代など、
国の支援45万7000円だけで補えない部分の家計シミュレーションをしてみることで、実際の負担額が明確になります。
就学支援金制度の仕組み|所得制限と課税所得とは?
1. なぜ「年収」ではなく“課税所得”を見る?
同じ年収600万円でも、住宅ローン控除・扶養控除・医療費控除など、家族構成や節税対策しているかによって家計の本当の余裕が違っているからです。
つまり、控除が多い世帯ほど課税所得が下がる為、年収ベースで計られないようにしているためです。
2026年度においては所得制限がなくなるため国からの授業料の就学支援金は45万7000円は対象になりますが、各自治体ごとの独自支援は課税所得が目安になる可能性があるので載せておきます。
実質年収は同じでも支援額が変わるケース
| 夫婦+高校生1人 | Aさん | Bさん |
|---|---|---|
| 年収(合計) | 600万円 | 600万円 |
| 控除活用 | ほぼなし | iDeCo月2万円+生命保険料控除 |
| 課税所得 | 高い | 低い |
| 市町村民税所得割額 | 31万円 | 28万円 |
| 2024年判定 | 支援対象外 | 私立で年11万8800円支援 |
Bさんは老後資金を積み立てつつ、支援金の対象にもなる
2.課税所得が減る要因をチェック
年収は家族構成は変えられませんが、控除を賢く使うことで課税所得を下げ、就学支援金や県の上乗せ補助を受けやすくなります。
では、どんな控除があるのかチェックしてみますと、
-
住民税課税通知書をチェック
→ 所得割額があと数万円下がれば支援区分が変わるか確認。 -
ふるさと納税シミュレーターで上限額を確認
→ 寄附→ワンストップ特例なら確定申告不要。 -
会社員なら年末調整提出締切を確認
→ 生命保険・地震保険の控除証明書を間に合わせる。 -
iDeCoは掛金変更申込書を急ぎ提出
→ 反映は申込翌月以降。ギリギリなら来年度以降の節税に。 -
医療費レシートは家族分まとめて保管
→ 10万円超 or 所得×5%超で医療費控除を選択。
控除をうまく活用することで、市町村民税の節税にもなりますよ。
【費用比較】公立vs私立 高校入学時にかかるお金&隠れたコストまとめ

ここからは2025年に公立・私立にそれぞれ進学した場合に係る費用について、かかる費用についてお伝えしていきます。
公立の初年度・毎年の費用のリアル
【公立高校A(地方都市の一例)】
-
授業料:0円(無償化対象)
-
入学金:約5,650円
-
学納金:約75,000円(PTA・施設費など)
-
タブレット(iPad10世代・保証込み):約65,000円
-
教科書・上履き・体操着など:約30,000円
-
学校管理費(年間):約120,000円
-
通学定期券代(例:3か月17,240円×年4回):約69,000円/年
-
私服購入代:約20,000円
初年度は授業料ゼロでも、約33万円程度の現金が必要。
さらに、部活によっては思わぬ出費(例:エレキベース約18万円、運動部は一式揃え約20万+遠征費)も発生するケースがあります。
※2025年度例。学校や地域によって差があるため、必ず説明会や公式資料でご確認ください。
私立の初年度・毎年の費用のリアル
【私立高校A(地方都市の一例)】
-
入学金:約12万円(専願入学で全額免除の例あり)
-
授業料:月額3.5万円(年間42万円)
-
維持費:月額7,500円(年間9万円)
-
制服:約7.5万円、タブレット:約6万円
-
教科書+副教材:約3.8万円
-
通学定期券代(例:6か月×2):約5~10万円/年
初年度は、就学支援金(最大39.6万円)が満額支給されても約40~50万円の負担が発生するイメージです。
入学金・制服代・教材・塾代…「見落としがちな出費」
【見落としがちな出費(公立・私立共通の例)】
-
塾・予備校代:年間約10万~50万円(学校の進度や進路希望による)
-
部活費:合宿費・遠征費・用具代など(例:年間5万~20万円、楽器や道具購入で数万円~十数万円)
-
修学旅行積立:年間約3万~5万円(学校や旅行先による)
-
制服・靴・かばんの買い替え:年間数千円~1万円(体形変化・破損時など)
-
タブレット・ICT維持費:年間5,000円~1万円(保険料・修理・更新費など)
-
模試・資格試験料(英検・数検など):年5,000円~2万円
-
PTA会費・後援会費:年間5,000円~1万円
-
通学定期券代:年間5万円~10万円(公共交通機関利用の場合)
公立私立の費用で重複する部分もありますが、授業料は無償や支援があっても、こうしたプラスαの出費が毎年重なります。
特に塾代や部活関係の費用は大きな負担になることもあるので、想定しておくと安心です。
申請の流れとその他利用できる支援や必要になる時期

上記を踏まえて、高校授業料無償化(就学支援金)はどのような流れで申請するのか、また他に利用できる制度や資金の準備についてお伝えしていきます。
申請の流れと注意点
高校授業料無償化の申請は学校側から書類が届きます。
期限に間に合わないと制度を利用できなくなってしまうので注意が必要です。
1. 申請時期はいつ?
高校入学後すぐに案内されるケースが多く、春(4〜5月)に手続きが集中します。
2. どこに申請するの?
支援制度は基本的に「学校を通じて」申請します。学校から配布される案内を見逃さないようにしましょう。
3. 必要な書類は?
-
住民税課税証明書
-
世帯全員のマイナンバー
-
保護者の本人確認書類 など
4. よくある注意点
-
期限に間に合わないと、その年度の支援が受けられない場合も!
-
世帯年収の確認は「前年の所得」で見られることが多いので要注意。
利用できる支援制度まとめ
国の高校授業料無償化の他に利用できる支援制度もあります。
そちらについてもまとめておきましたので、ご参考にしてみてください。
1. 高等学校等奨学給付金
対象:公立・私立高校に通う生徒のうち、住民税非課税世帯など
支給額(目安):年額3~13万円(教材・修学旅行費等の補助)
ポイント:
・授業料以外の費用をサポートしてくれる
・就学支援金と併用可能
2. 地方自治体の独自支援
内容例:
・入学準備金
・PTA会費等の補助
・修学旅行費助成
確認方法:お住まいの市区町村の教育委員会に問い合わせ
3. 教育ローン・奨学金
主なもの:
・日本政策金融公庫「教育一般貸付(国の教育ローン)」
・都道府県・民間の奨学金
特徴:
・審査がある
・無利子・有利子など種類多数
・緊急の場合、申込から融資まで早いものも
4. 学校独自の支援
例:
・特待生制度(学費減免)
・入学金減額制度
・成績優秀者向けの奨学金
入学までのお金|時期ごとに必要な費用まとめ
私立は合格が決まるとすぐに入学金の支払いが発生します。
実際どのような流れでいつお金が必要なのかをお伝えしておきますね。
\ いつ・いくら必要?高校入学までのお金の流れ /
【合格発表】
↓
▸ 入学金支払い(約20万〜30万円)
【注意】合格発表から10日以内が多い
↓
【入学説明会(3月ごろ)】
↓
▸ 制服・体操服・上履き・教材などの購入(約10万〜15万円)
▸ PTA会費・施設費など初年度分(約5万〜10万円)
↓
【入学式】
↓
▸ 授業料(就学支援金で軽減可/私立は月3万円程度)
▸ タブレット・学用品の購入(5万〜10万円)
↓
【入学後(6月ごろまで)】
↓
▸ 修学旅行費の積立などがスタート
お金が足りないときの解決策
学資保険や貯蓄で準備してある方もいらっしゃるかもしれませんが、
準備してない!どうしよう?
という方にどんな方法があるのかお伝えします。
教育ローンを利用する
-
国の教育ローン(日本政策金融公庫)
低金利&固定金利で、入学前の資金調達にも対応。
➡ 審査期間は約2週間なので早めに動くのが安心。 -
銀行・信用金庫などの教育ローン
民間は審査が早く、最短即日融資も。
奨学金を検討する
-
入学前予約型の奨学金(都道府県や学校独自のものがある)
➡ 入試の段階で申請ができる場合も。
自治体の支援を確認
-
一時的な「入学準備金」などを出している自治体も。
➡ 住んでいる市区町村の公式サイトで確認!
家計の立て直し&一時的な借入れ
-
親族に一時的に借りる
➡ 金利負担がなく柔軟に返せるケースも。 -
家計の見直し(固定費削減など)
➡ スマホ代・保険・サブスクなどを整理して一時的に補填。
分割・延納を相談する
-
学校に相談する
➡ 授業料の「分割払いや納付期限の延長」に応じてくれる場合あり。
間に合わなかった…という声もじっさいあるので、まずは早めに学校や市区町村に相談をしてみてください。
最後に|親子で進路を決める前に考えるべきこと

費用については、公立でも私立でもまとまったお金が必要になりますが、一番はお子様自身が本当に行きたいと思える学校に進むこと。
受験するのはお子様です。
望む進路に向けてできる準備をしながらがんばれと応援するのみです。
学校が決まるまで、まずは成績のことで頭を痛めることもあるかと思いますが、一番頑張らなければならないお子様を精一杯応援してあげてくださいね。
お子さんが自信を持って受験に挑めるよう、制度とお金の不安を少しでも軽くできますように――。
2026年、皆さんの桜が笑顔で咲きますよう願っています。
もちこ