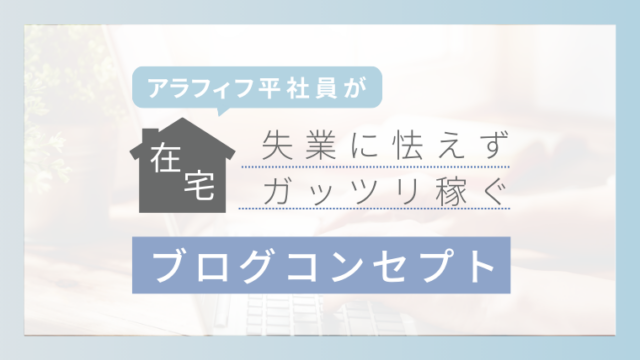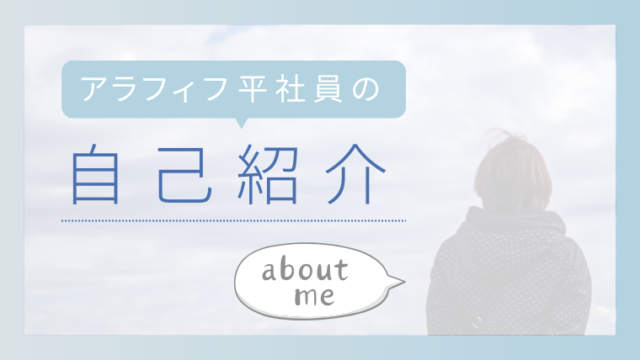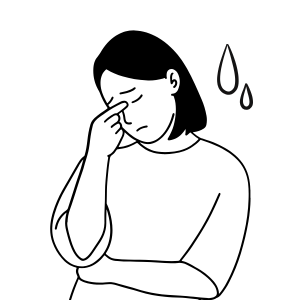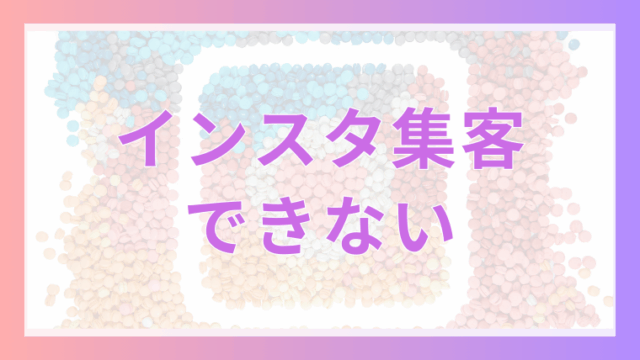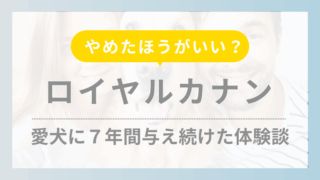こんにちは、フリーランスでSNS運用代行をしているもちこです。
そんなふうに悩んでいませんか?
私自身も、プロフィールを整えて、コンセプトを決めて、投稿も続けていたのに──
全く集客につながらない時期がありました。
いくら努力しても反応が薄く、「インスタ集客できないのは、自分に才能がないから?」と落ち込んだこともあります。
でもあるとき、一度作ったターゲットを思い切って見直したことで、流れがガラッと変わったんです。
最初の頃、なんとなく決めていたターゲットでは、本当に来てほしいお客さんには届いていなかった。
つまり、「インスタ集客できない状態」を、自分でつくってしまっていたんです。
うまくいかず悩んでいるなら、今のターゲットを見直すことが突破口になるかもしれません。
そのままでは、これからも集客できない状態が続いてしまう可能性だってあります。
「ターゲットのこと、あまり深く考えていなかった…」
そんな方にこそ読んでほしい、本気のターゲット設定について、わかりやすく解説していきます。
そもそも、なぜインスタでターゲット設定が必要なの?

インスタのターゲット「なんとなく」では届かない
がんばって投稿しているのに「いいね」も「保存」も増えない…
その原因のひとつだと考えられるのが、ターゲットがあいまいなことです。
なんとなく決めたターゲットに向けて、ただただ自分の伝えたいことばかりとうこうしてしまうと、言葉や投稿がズレてしまい誰にも刺さりません。
「忙しいママ」なのか「副業を始めた人」なのかで、同じ内容でも伝え方は全く違います。
たとえば、それぞれのターゲットにインスタ投稿を継続するコツをテーマにすると…
忙しいママ向け投稿は↓
子どもが寝たと思ったら泣き出して、インスタ書こうと思ったのに何もできなかった…なんて日もありますよね。
そんなとき、“1週間に1投稿でもOK”って決めたら、ちょっと心が軽くなりました。
完璧じゃなくて大丈夫。大切なのは“続けられるゆるさ”です。
副業中の会社員女性向け投稿になると↓
仕事終わりにインスタ更新、正直きついですよね。でも、“3日に1回でもOK”って決めたら、ラクになりました。
大事なのは【継続】じゃなく【自分に合ったペース】を作ること。
無理なく続けてこそ、成果につながります。
同じ内容でも言葉でイメージされるシーンは全く違います。
設定していないと発信がブレる・続かない・反応がこない
ターゲットがぼんやりしていると、発信もどこかあいまいになってしまいます。
今日はママ向け、明日は副業女子へ……そんなふうに毎回届ける相手が変わると、結局“誰にも届かないラブレター”を送り続けるような状態に。
「これは、まさに私のための投稿だ!」
そう思ってもらうには、「誰に届けるか」をハッキリさせることが欠かせません。
さらに、ターゲットが決まっていないと、
「何を書けばいいか分からない」
「反応がなくてやる気が出ない」
──と発信が続かない原因にもつながります。
実は、モチベーションが下がる一番の理由は“誰に向けて発信しているのか分からない”ことかもしれません。
万垢はなぜターゲット設定を重視しているのか?
フォロワー1万人越えのいわゆる万垢の方たち。
実は、「誰に何を届けるのか」を徹底的に設定する姿勢があります。
この方々はこのターゲット設定をとても重視しておりますが、なぜなのか?
それは、ターゲットを決めることで、たった一人の人にだけ刺さる言葉選びに力を注いでいるからです。
先に書いたようにターゲットによって刺さる言葉が違うから、一番届けたい人に刺すための言葉選びはとても緻密です。
その緻密さこそが共感されるかされないかの差に繋がることを知っているからだといいます。
万垢の方たちはターゲットに合わせて言葉、価格、考え方まで計算しています。
実際に私も万垢の方たちからインスタ運用を学ぶ中で、投稿の表現だけでなく、そもそも誰に書いているかがすべてを決めるということに気づきました。
ターゲットは想像するのではなく、インスタの中で見つけて言葉を選ぶだけで、投稿を見てもらうフォロワーの方が変わっていったことを実感しました。
それでは、実際どのように設定するのかお伝えしていきますね。
まずは3C分析で“全体の地図”を持とう

プロフィールを整えたのに反応がない。
発信をがんばっているのに、集客につながらない。
──そんなときは、「誰に・何を・どう届けるか」の全体像が曖昧になっているのかもしれません。
そこでまず活用したいのが、マーケティングの基本である「3C分析」。
これは、次の3つの視点から発信を整理するためのフレームワークです:
🔸Customer(相手):誰に届ける?
🔸Competitor(競合):似た発信とどう違う?
🔸Company(自分):自分の強み・経験は?
この3つを順番に見ていくことで、自分の発信の“地図”がクリアになり、ブレない軸ができていきます。
【Customer(相手)】インスタで誰がどんな悩みを持っている?
まず考えるべきは、「誰に届けたいのか?」という視点です。
たとえば──
✔ 毎日投稿しているのに反応がない
✔ 何を発信していいのかわからない
✔ デザインがイマイチで自信が持てない
そんな悩みを抱える人が、あなたの投稿を必要としているかもしれません。
📍 年齢・ライフスタイル・SNSとの関わり方
📍 どんな不安や願望を持っているか
📍 検索のときに使う言葉はどんなものか
ここまで見えてくると、「誰に響かせるか」が明確になります。
【Competitor(競合)】似た発信をしている人と、自分の違いは?
「競合」と聞くと、つい“ライバル”のように感じてしまいますよね。
でも、本当に大事なのは「勝ち負け」ではなく、
“自分がどこで、誰に向けて発信するのか”というポジションを見つけることです。
たとえば──
✔ 同じテーマでも「初心者向け」「忙しいママ向け」など、届ける相手が違う
✔ デザインで惹きつける人もいれば、言葉で寄り添う人もいる
つまり、同じジャンルでも切り口や伝え方によって、発信の世界は大きく変わるということ。
ここで気になるのが、「ブルーオーシャン(競合が少ない未開拓領域)」という考え方。
「誰もやっていないところを狙えば勝てる」と思いがちですが、
インスタの世界では、もはや完全なブルーオーシャンは存在しないとも言われています。
なぜなら、誰もいない=ニーズがない可能性が高いから。
つまり、発信したいテーマにすでに多くの競合がいる「レッドオーシャン」の中で、
“自分にしかできない切り口”を見つけていく必要があるということです。
だからこそ、競合をしっかり観察して、
「どんな人が」「どんな届け方をしているのか」を知ることが、
「じゃあ私はどうする?」というポジションを見つけるための重要なステップになります。
【Company(自分)】自分が届けられる強み・経験・価値は?
最後に、自分自身を棚卸ししてみましょう。
✔ これまでの仕事や経験
✔ 乗り越えてきた悩み(=誰かの希望になる)
✔ 自然とアドバイスしていること
“強み”とは、スキルだけではありません。
「過去の自分に教えてあげたかったこと」こそが、誰かの役に立つ発信になります。
3つの視点が重なる場所=ポジショニングの起点
3Cの視点が重なるところこそが、自分自身が発信する意味のある場所です。
たとえば、
【Customer】「自己流でがんばっているけど、インスタ集客がうまくいかない40代女性」
【Competitor】「情報は多いけど、感覚的でわかりにくい発信が多い」
【Company】「感覚じゃなく、設計と仕組みでインスタを整えるのが得意な私」
この3つが重なる部分が見えたとき、そこがあなたのポジショニングの起点になります。
一度決めたら終わり、ではありません。
発信を続けながら、何度も見返して軌道修正することで、“今の自分にぴったり合ったポジション”が見つかっていきます。
ターゲットとペルソナはどう違う?順番を間違えないで
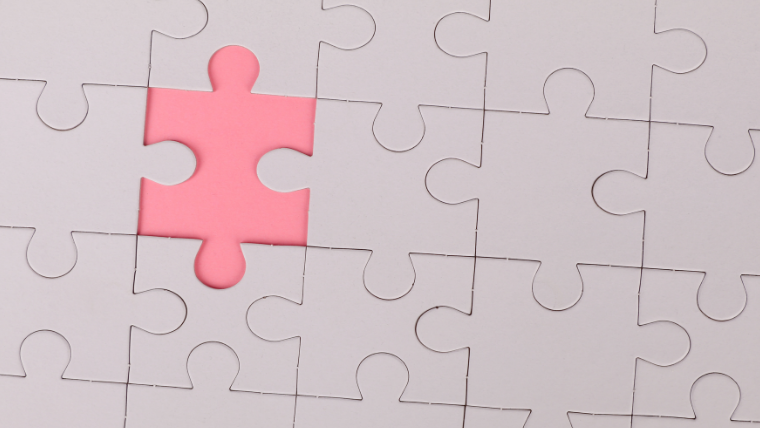
ペルソナが大事って聞いたけど、ターゲットとどう違うの?一緒じゃない?
そんな疑問ありませんか?
この2つは混同されやすいのですが、実は役割も設計の順番も全く違うんです。
ターゲット=ざっくりした層、ペルソナ=象徴的な1人
まず押さえておきたいのが、ターゲットは「層」、ペルソナは「人物」だということ。
-
ターゲット:30〜40代の働くママ
-
ペルソナ:フルタイム勤務で2人の子育て中、SNSで情報収集しているけど投稿には消極的な「佐藤由美さん(38歳)」
このように、ターゲットは「大まかな属性グループ」であり、ペルソナは「その中の代表的な1人をリアルに描いた存在」です。
投稿を作成するとき、このペルソナを3次元で思い浮かべられる位解像度を高くすると、「この人に届けたい!」で発信の軸がぶれにくくなりますよ。
「1人に絞ればいい」はペルソナ設計の話
よくある誤解は、
ターゲットは1人に絞るべき。
この誤解を生じるターゲットという言葉はペルソナのこと。
ターゲットは30代から40代のママというようなたくさんいる層のことだということを間違えないようにしてくださいね。
では、
そんな不安がある方に向けて、**ペルソナ設計でやりがちな“致命的なミス”**とその解決法をまとめた記事はこちら▼
誰も教えてくれない…インスタ集客が失敗する【ペルソナ設計の致命的なミス】とは?
まずはターゲットを“観察”して“ペルソナ化”する流れが正解
では、具体的にどうやってターゲットとペルソナを考えるのか?といいますと、
答えは、まずターゲットを観察することから始めてみてください。
🔸SNSでよく見かける投稿の傾向
🔸コメント欄の悩みや言葉づかい
🔸同じ層の人が「どこに困っているか」「何を求めているか」
こうした情報を集めながら、「この人、まさにこんな悩みを持っていそうだな…」と思える象徴的な1人つまりペルソナを立てていく流れです。
🔹ターゲットという森を見て、森の中の木を選ぶイメージで設計していきます。
🔹では次に実践ステップでどうやって行くのか具体的に見ていきましょうね。
インスタでのターゲット設定【実践ステップ】

Step1|競合アカウントを10〜20個見て、「誰に届けているか」を観察する
まずは、自分と似たテーマで発信している競合アカウントを10〜20個ほどリサーチしてみましょう。
🔹どんな人に向けて発信していそう?(ターゲット層)
🔹投稿のトーンやデザインはどんな雰囲気?
🔹フォロワー数に対して、どれくらい反応がある?(いいね・保存・コメント)
実際に万垢を達成した人たちは、20以上のアカウントを比較・分析して、「フォロワー数と内容の質のバランス」や「投稿の届け方」を見極めています。
❌ 見ても意味がないアカウント例:
✔ 投稿が止まっている(1か月以上更新なし)
✔ リールやストーリーなど、今の機能を使っていない
✔ フォロワーは多いのに、反応(エンゲージメント)が明らかに少ない
→ これらはいわゆる“死にアカウント”です。
現在のInstagramアルゴリズムには乗っていないため、参考にしても意味がないことが多いです。
ただ“数”をこなすのではなく、今もアクティブで、反応のある競合アカウントを選ぶのが、成功への近道です。
Step2|コメント欄・プロフィール・ハイライトから“リアルな人”を見つける
次は、競合アカウントのフォロワーや投稿への反応から、“どんな人がその発信を見ているのか”を読み取ります。
特に注目すべきポイントはこちら
✔ コメント欄の言葉づかいや悩み
✔ フォロワーのプロフィール(肩書・投稿内容)
✔ ハイライトにある「お客様の声」や「よくある質問」など
✔ ストーリーでのリアクションやQ&Aのやりとり
「どんな言葉に反応しているか」「何を求めているか」を読み解くことで、机上のターゲット像ではなく、“リアルな人物像”に近づけることができます。
Step3|“感情や悩みベース”で仮ターゲットを言語化する
ここでは、競合観察から得た情報をもとに、「この人に届けたい」という仮ターゲット像をリアルに描き出します。
属性だけでなく、「感情」や「行動」「思い込み」「葛藤」にまで深掘りするのがポイント。
たとえば、こんなふうに描けるか、がポイント
📍「Instagramをがんばっているけど、反応がなくて“向いてないのかも”と思いはじめている40代女性」
📍「投稿はしてるけど、“届ける相手”を考えたことがない」
📍「本当は誰かの役に立ちたいけど、自分の発信に自信が持てない」
解像度を上げるには、「悩みを100個書き出す」のが効果的
仮ターゲットをよりリアルにするためには、その人の“悩み”をできるだけたくさん出してみること。
おすすめは、「○○だけど●●ではない」という形式で書き出すことです。
例:「○○だけど●●ではない」フォーマット
-
投稿してるけど、見てもらえてる気がしない
-
フォロワーはいるけど、誰が見てるかわからない
-
インスタ集客したいけど、売り込みっぽくしたくない
-
SNSは苦手だけど、仕事には使いたい
-
いいねはつくけど、仕事につながらない
-
すでに情報は発信してるけど、ターゲットは決めてない
-
デザインは整えたけど、肝心の中身が決まらない
-
人の投稿は見てるけど、自分は何を出せばいいかわからない
このように、「矛盾」「揺らぎ」「理想と現実のギャップ」があると、人間味が出て、投稿設計のヒントになります。
補足:悩みのジャンルごとに分けて書くと、100個に届きやすくなります。
📍投稿の悩み
📍見られ方の悩み
📍時間・継続の悩み
📍自信・不安・比較の悩み
📍集客・成果の悩み
この悩みリストは、投稿テーマやストーリーの引き出しにもなる宝物です。
Step4(投稿への反映)がスムーズになるだけでなく、見返すたびに発信が“ぶれにくく”なりますよ。
Step4|自分の強みを生かして、投稿テーマを“その人”に合わせてズラす
仮ターゲットが見えてきたら、いよいよ投稿に反映させていきます。
ここで大切なのは、「伝えたいこと」ではなく「その人が受け取りやすい形」に変えることです。
なんだか、難しそう…って思っちゃいますよね。
私も自分には何もないから…って思っていました。
でも、細かい作業が好き、とか、二人の子育てをしてきたママだから、子供の好きなものがわかるよ!のように、ちょっとした自分のここが得意ということが強みになりますよ。
たとえば、こんなかけ合わせが…
📍自分の強み:デザインが得意
→「Canvaでできる、おしゃれ×時短プロフィール」
📍自分の強み:言語化が得意
→「5分で言語化!“モヤモヤしてた想い”がスッと伝わるプロフィール」
📍自分の強み:お客さんの声を集めるのが得意
→「お客様の声から逆算!共感されるプロフィールの作り方」
こんな視点で考えてみてください
🔹「その人が悩んでること × 自分が助けてあげられること」
🔹「相手がつまずいてること × 自分が乗り越えてきた経験」
🔹「相手が求めてる雰囲気 × 自分の世界観やトーン」
この「相手と自分の交差点」にあるテーマこそが、“刺さる投稿”であり“自分らしい発信”になります。
仮ターゲットに合わせてテーマを調整するだけでなく、あなたの強みや得意分野を盛り込むことで、“選ばれる発信”に変わります。
Step5|伸びた投稿の反応から、ターゲットを修正し続ける
ここまで、本当にお疲れさまでした。
大変でしたよね。その気持ち、すごくよくわかります。
私もこのプロセスに何度も悩み、手が止まった経験があります。
でも、ここまでターゲット設定と真剣に向き合ったことが本当に凄いなと思います。
ひとまず、ターゲット設定の“仮完成”にたどり着きました。
とはいえ、これはあくまで“スタート地点としての完成”です。
なぜかというと──
いざ投稿を始めてみると、「あれ?思ってた反応と違うな」ということが、ほぼ確実に起きるからです。
一発で“正解のターゲット”は見つからない
発信してみて初めてわかること、届いてみて気づくこと。
ターゲット設計は、机の上では完成しません。
だからこそ、
📍投稿ごとの反応
📍フォロワーの傾向
📍伸びた投稿に共通するポイント
──こういった“リアルな反応”を見ながら、定期的に見直していくことが大事です。
アカウントは「育てていくもの」
最初から完璧を目指さなくて大丈夫ですよ。
投稿→反応→調整というサイクルをくり返すことで、少しずつ「しっくりくるターゲット像」が育っていきます。
あなたのアカウントは、あなたと一緒に成長していきます。
焦らず、楽しみながら、発信を続けてみてくださいね。
ターゲット設計 × ツール活用法

全部自分でやってみてこれで大丈夫かな…って思いますよね。
だれかに聞いてほしい、これでいいのかちょっとヒントも欲しい。
そんなふうに、1人で悩みながらターゲット設定に向き合っている方へ。
今は、もう“うんうん唸って一人で抱え込む時代”ではありません。
でも今は、AIを“壁打ち相手”として使うことで、発信設計が何倍もラクに&深くなる時代です。
もう自分ひとりで悩む時代じゃない
ターゲット設計でつまずくのは、インスタと真剣に向き合う誰もが通る道です。
でも最近は、考えを“見える化”して整理する相棒=ツール(ChatGPTなど)がありますよね。
これは、自分で考えてみて、その答えをAIに投げかけてみることで、1人では考え付かなかった部分を深堀してくれる相棒のような存在になりますよ。
ChatGPTでペルソナ案を出す/競合リサーチを整理する
どんな風に活用するのか次のように投げかけてみてください。
🔹例:「インスタ投稿に悩む40代女性のペルソナを出して」と聞いてみる
🔹競合アカウントを羅列して「比較表にまとめて」と依頼もOK
活用しやすいようにテンプレを準備しましたので、コピペしてご活用してみてくださいね!
【ChatGPT活用例テンプレ】〜ターゲット設計編〜
①|ペルソナ案を出すとき
例
「40代の女性で、Instagramをがんばってるけど集客につながらず悩んでいる人のペルソナを、できるだけリアルに3人出して。名前・年齢・家族構成・生活習慣・SNSに対する気持ち・悩み・よく使う言葉も教えてください。」
ポイント
🔸ペルソナの数は「1〜3人」に絞ると使いやすい
🔸「生活習慣」「感情ベース」「口ぐせ」を含めるとリアル度アップ
②|競合アカウントの比較を整理するとき
例
「この3つのInstagramアカウントを比較して、届けている相手・投稿の特徴・反応の傾向を表にしてまとめてください。
@〇〇 @〇〇 @〇〇(←実際のアカウント名)」
※アカウントURLでもOK
ポイント
🔸「自分が気になっている競合」を入れて比較させる
🔸表形式で整理してもらうと違いが視覚化しやすい
③|自分の強みや切り口を見つけるとき
例
「私はCanvaを使った投稿デザインが得意です。Instagram初心者の女性起業家向けに、私の強みを活かした発信テーマを10個考えてください。」
ポイント
🔸自分のスキル or 経験を一言添えて質問する
🔸「〇〇が得意」「〇〇の経験がある」と伝えると精度が高くなる
使い方のコツ
AIに聞くときは、「背景(誰向け)」「目的(何がしたい)」「制約(数・形式)」を入れると、より実用的な回答になります。
AIは“丸投げ”じゃなく、“観察と確認”に使うのがコツ
AIはとっても便利なツールですが、出された答えがすべて正しいとは限りません。
ときには、全く見当違いな情報や、現実とズレた内容を出してくることもあります。
だからこそ、答えをそのまま信じて使うのではなく、あくまで「1つの視点」として受け取ることが大切です。
「なるほど、こういう見方もあるんだな」と、参考意見として観察する姿勢がちょうどいいバランスです。
信頼できるかどうかは、最終的に自分で判断する必要があります。
AIは“正解をくれる先生”ではなく、“壁打ち相手”のような存在。
主導権は常に自分にあると意識して、「自分の軸」を持って使うことで、アウトプットの精度もグッと上がります。
使うときのポイントは、壁打ちして出てきた回答に対して、さらに
「なぜそう判断したの?」「他の可能性はある?」
と問いかけてみると、より深いアイデアや視点が引き出せます。
このようにして使えば、AIは発信設計の強力なパートナーになります。
大事なのは、“任せきり”ではなく、“対話しながら使う”姿勢です。
まとめ|ターゲット設定は“売れる設計図”の第一歩
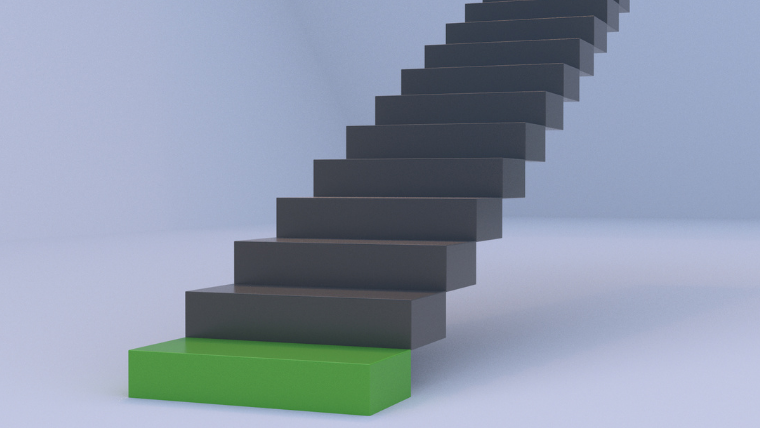
「届けたい人」が決まれば、「届け方」も自然に決まる
「届けたい人」が決まれば、「届け方」も自然に決まっていきます。
誰に届けるかが見えた瞬間、言葉も、デザインも、迷わずサクッと決まっていくのではないでしょうか?
ターゲットの悩みと真剣に向き合うことで、ペルソナの解像度はグンとアップします。
好きなもの、発する言葉、行動パターンまで、まるで目の前にいるかのように手に取るように感じられるはずです。
「なんでこんなに投稿に迷うんだろう…」と感じていたのは、
もしかすると、そのペルソナの姿が頭の中の“空想の人”から抜け出せていなかったからかもしれません。
でも、きっと大丈夫。
あなたの届けたい想いが、たった一人の“本当に届けたい人”に届く日は、すぐそこまで来ています。
それくらい、ターゲット設定は大切な「売れる設計図」の第一歩なんです。
まずは“今そこにいる1人”を見つけることから始めよう
「届けたい人に届ける」って、思っていたよりずっと難しい。
実際に手を動かしてターゲット設定をしてみると、
「あれ…?こんなに決めるの大変なんだ」と感じるかもしれません。
そんなときは、まずは自分の身近な人を想定してみるのがおすすめです。
たとえば、
✔ 過去の自分
✔ 友人
✔ SNSでよく見かける“あの人”
身近な人であれば、どんなことに悩んでいるのか、どんな言葉を使っているのかも思い浮かびやすく、時には直接聞くこともできます。
完璧じゃなくても大丈夫です!
まずは“仮”でもいいから、ターゲットを描いて、自分の言葉で届けてみる。
きっと、そこから“インスタ発信がしっくりくる感覚”が、少しずつ育っていきます。
長い文章でしたが、最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。
もちこ
次は「ペルソナ設計」を深掘りしたこちらの記事もどうぞ
誰も教えてくれない…インスタ集客が失敗する【ペルソナ設計の致命的なミス】とは?